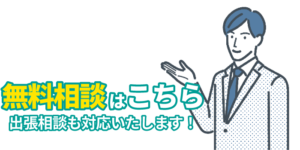遺言書にこんなイメージありませんか?
まだ先のことだし
家族みんな仲がいいし
なんとなく面倒くさい
そもそも何を書くの
書くことがまとまらない
親に書いてもらっといた方がいいかな?
一度書いたら変えられない?
書いてしまった内容にしばられる?
書いた預金はひきだせない?
遺言って撤回できない?

こんなときのために作っておきましょう
【遺言書を作っておいた方がいい例】
・お子様がいない
・配偶者がいない
・相続人が兄弟だけ
・前妻(前夫)との間にお子様がいる
・介護等している親族にお子様がいない
・孫に相続したい
・子供の妻などに財産分けをしたい
・献身的に介護をしてくれた人がいる
・貢献してくれた人、団体がいる
・寄付を考えている
・事業を承継したい
遺言書にこんな
イメージありませんか?

まだ先のことだし
家族みんな仲がいいし
なんとなく面倒くさい
そもそも何を書くの
書くことがまとまらない
親に書いてもらっといた方がいいかな?
一度書いたら変えられない?
書いてしまった内容にしばられる?
書いた預金はひきだせない?
遺言って撤回できない?
こんなときのために
作っておきましょう

【遺言書を作っておいた方がいい例】
・お子様がいない
・配偶者がいない
・相続人が兄弟だけ
・前妻(前夫)との間にお子様がいる
・介護等している親族にお子様がいない
・孫に相続したい
・子供の妻などに財産分けをしたい
・献身的に介護をしてくれた人がいる
・貢献してくれた人、団体がいる
・寄付を考えている
・事業を承継したい
【遺言書がないことで起きた事例】
事例1
相談者 60代・男性
≪叔母の成年後見人になった方の遺産分割での事例≫
相談内容
県外にすんでいた叔母が認知症になりました。
叔母には子供がなく、ご主人も高齢で、甥であった相談者が県外に通いご主人の介護を懸命に行っておりました。
しかし認知症の叔母の介護は同時にできない為、叔母の姉が県内に引取り介護施設へと入所させる段取をとっておりました。ところが懸命に介護をしていたご主人が急逝してしまったのです。
叔母の姉も高齢で、相続等の段取もわからず、叔母の入所も重なり成年後見人を立てざる負えなくなったところにその甥である相談者のところに白羽の矢が立ちました。そこで甥は善意で成年後見人になることとしました。
解決
相談者(甥)の知人でもあった私が、相談にあたり調査に入ると、叔母の旦那様には、叔母と入籍する前に前妻がおり、その間に一人のお子様がいることが判明しました。
相談者には当然面識もなく、さらに叔母の姉もその存在を知らず、旦那様の法定相続人は、叔母とその子供ということになりました。また、ご主人は遺言書などを残していなかった為、その子供の捜索から開始いたしました。
結果、ご主人と前妻は、お子様が幼少期の時に離婚されていたため甥と面識が無く、遺産分割協議においても成年後見人の甥と面識のないお子様で進める形となりました。
善意で成年後見人になった相談者(甥)は法定相続人ではない為遺産分割の対象とはなりません。当然無報酬です。そこで当職より遺産分割協議後、これまで貢献した甥へのお礼の一部として遺産より、贈与契約を結びませんか?と提案したところお子様は快く承知いただけました。
ポイント
相続は相続人確定の段階で誰もしらなかった相続人が現れることもあります。さらに超高齢社会で相続人が認知症になるリスクも高まっております。認知症になる前に、遺言書の作成等をしておいていた方が、相続人にとっても良い結果になる可能性が大きいと思います。
また、今回の場合は、相続人の方の理解が得られたため、懸命に介護をし無報酬だった成年後見人(甥・法定相続人ではない)へも贈与という形で結果が出せ良かったと思いますが、相続に関する手続きを相続人でもない方がなされるケースも多々あります。遺言書の作成を検討する方が良い事例ではないでしょうか。
事例2
相談者 60代・男性
≪今の時代を象徴する遺産分割の事例≫
相談内容
叔母が亡くなりました。
叔母には子供がなく、両親も他界していたため、相続人は叔母の兄弟・姉妹となりました。
しかし、相続人になる兄弟・姉妹は昭和初期の生まれで亡くなっている方も多く、その子にあたる甥、姪が代襲相続者となり遺産分割協議をすることとなりました。
兄弟・姉妹・甥・姪含め 10 人になる遺産分割協議です。
解決
相続人が兄弟、姉妹、甥、姪と多数にわたる相続だったため難航することが予想されました。
県外在住者も多く、相続人調査(委任状)の段階よりお手紙等でのやり取りがほぼ全部という状況でした。相続財産が多く、遺言書も無かった為、遺産分割協議が必要となったのですが、相続人様同士は親戚ではありますが親戚付合いはほぼ無い状況でした。
当職で遺産分割協議書(案)を作成し、どうにか 9 名の同意を得られ、分割協議に移る過程に入りましたが、お一人の相続人の方からのお返事を頂けず沈黙状態となりました。
代表相続人の方とお話し合いをしたところ、亡くなられた叔母の兄弟の子(甥・相談者様のいとこ)にあたられえる方ですが、その兄妹の方でも連絡を 30 年以上取っていないらしいとのことでした。
さらに、兄妹と話を進めるとその相続人は生活保護を受けているのではないかという情報があり、連絡方法は電話(固定・携帯)等も無いため、手紙での連絡が取れないことに現状では面会での対応にならざる負えない状況でした。県外在住の為、代表相続人、代表相続人兄、その方の兄妹、当職で面会にお伺いいたしましたが、その相続人の方は一方的に「これは詐欺だ」・「兄妹・いとこも含め全員昔と顔が違う、他人がなりすましている」・「手紙一つでお金(相続財産になるのですが)が入るなんて詐欺だ」・「昨今の新聞でも書いてある詐欺だから警察に行こう」ということになり近所の交番へ行くことになりました。警察には資料を含め経緯を説明致しましたが、警察の民事不介入によりその場では解決出来ない形になりました。
結局、弁護士法に抵触する恐れ(弁護士法72条)があり、当職では解決できない案件となり、提携の弁護士に依頼することとなりました。
結局、その相続人の方は裁判所より呼出しがあり、県外より裁判所に出頭することとなりました。
その後、遺産分割申立事件になり審判という形でその相続人は相続分の放棄をし残りの9名での相続という結果になりました。
ポイント
今回の事例では、今の社会情勢(特殊詐欺等)の話が問題となっており特殊な事例かと思います。
通常のプラス財産が多い遺産分割事例であれば分与される側がいわゆる得(?言い方は良くないかもしれませんが)になる事例だと思いますが、昨今の社会情勢を考えるとそう思ってしまう方もいらっしゃるのかもしれません。
今回の事例に関わらず、調停・審判という形になりますと最低半年以上の年月がかかります。
(令和2年の司法統計によると、遺産分割事件の審理は6カ月から1年が最も多く、ついで1年から2年、中には3年を超える事案も多々あります)
さらに費用も当然にかかります。(遺産は減りますし、別のあらぬ争族を引き起こします。)
今回の事例の場合、通常は生活保護法の観点より、法律的には相続人は受給拒否は出来ないのではないかと思います。
ですが、個人情報保護法の関係上、区・市役所等からのなんの情報も公開がされず(本人が生活保護を受けているかどうか、また、情報公開されないのであればケースワーカーから相続人に説明してほしいと申し伝えましたが)連絡も取れない状況に陥ってしまいました。
通常であれば生活保護費は税金で賄われているため生活保護の一次支給停止等の措置が必要になるものではないかと思いましたが、区・市役所等からの遺産分割協議への協力は皆無でありました。
以上のように昨今ではこのような事例が出てきております。
大切な家族・親族等の為に遺言書の作成をされることが良い事例ではなかったでしょうか。
(追記として、昭和初期のご兄弟の中には生れてすぐに養子縁組でブラジルに行かれた方もいらっしゃいました。その方の消息は不明で、不在者財産管理人を専任した事例でもありました。)
遺言書がないことで
起きた事例
事例1
相談者 60代・男性
≪叔母の成年後見人になった方の
遺産分割での事例≫
相談内容
県外にすんでいた叔母が認知症になりました。
叔母には子供がなく、ご主人も高齢で、甥であった相談者が県外に通いご主人の介護を懸命に行っておりました。
しかし認知症の叔母の介護は同時にできない為、叔母の姉が県内に引取り介護施設へと入所させる段取をとっておりました。ところが懸命に介護をしていたご主人が急逝してしまったのです。
叔母の姉も高齢で、相続等の段取もわからず、叔母の入所も重なり成年後見人を立てざる負えなくなったところにその甥である相談者のところに白羽の矢が立ちました。そこで甥は善意で成年後見人になることとしました。
解決
相談者(甥)の知人でもあった私が、相談にあたり調査に入ると、叔母の旦那様には、叔母と入籍する前に前妻がおり、その間に一人のお子様がいることが判明しました。
相談者には当然面識もなく、さらに叔母の姉もその存在を知らず、旦那様の法定相続人は、叔母とその子供ということになりました。また、ご主人は遺言書などを残していなかった為、その子供の捜索から開始いたしました。
結果、ご主人と前妻は、お子様が幼少期の時に離婚されていたため甥と面識が無く、遺産分割協議においても成年後見人の甥と面識のないお子様で進める形となりました。
善意で成年後見人になった相談者(甥)は法定相続人ではない為遺産分割の対象とはなりません。当然無報酬です。そこで当職より遺産分割協議後、これまで貢献した甥へのお礼の一部として遺産より、贈与契約を結びませんか?と提案したところお子様は快く承知いただけました。
ポイント
相続は相続人確定の段階で誰もしらなかった相続人が現れることもあります。さらに超高齢社会で相続人が認知症になるリスクも高まっております。認知症になる前に、遺言書の作成等をしておいていた方が、相続人にとっても良い結果になる可能性が大きいと思います。
また、今回の場合は、相続人の方の理解が得られたため、懸命に介護をし無報酬だった成年後見人(甥・法定相続人ではない)へも贈与という形で結果が出せ良かったと思いますが、相続に関する手続きを相続人でもない方がなされるケースも多々あります。遺言書の作成を検討する方が良い事例ではないでしょうか。
事例2
相談者 60代・男性
≪今の時代を象徴する
遺産分割の事例≫
相談内容
叔母が亡くなりました。
叔母には子供がなく、両親も他界していたため、相続人は叔母の兄弟・姉妹となりました。
しかし、相続人になる兄弟・姉妹は昭和初期の生まれで亡くなっている方も多く、その子にあたる甥、姪が代襲相続者となり遺産分割協議をすることとなりました。
兄弟・姉妹・甥・姪含め 10 人になる遺産分割協議です。
解決
相続人が兄弟、姉妹、甥、姪と多数にわたる相続だったため難航することが予想されました。
県外在住者も多く、相続人調査(委任状)の段階よりお手紙等でのやり取りがほぼ全部という状況でした。相続財産が多く、遺言書も無かった為、遺産分割協議が必要となったのですが、相続人様同士は親戚ではありますが親戚付合いはほぼ無い状況でした。
当職で遺産分割協議書(案)を作成し、どうにか 9 名の同意を得られ、分割協議に移る過程に入りましたが、お一人の相続人の方からのお返事を頂けず沈黙状態となりました。
代表相続人の方とお話し合いをしたところ、亡くなられた叔母の兄弟の子(甥・相談者様のいとこ)にあたられえる方ですが、その兄妹の方でも連絡を 30 年以上取っていないらしいとのことでした。
さらに、兄妹と話を進めるとその相続人は生活保護を受けているのではないかという情報があり、連絡方法は電話(固定・携帯)等も無いため、手紙での連絡が取れないことに現状では面会での対応にならざる負えない状況でした。県外在住の為、代表相続人、代表相続人兄、その方の兄妹、当職で面会にお伺いいたしましたが、その相続人の方は一方的に「これは詐欺だ」・「兄妹・いとこも含め全員昔と顔が違う、他人がなりすましている」・「手紙一つでお金(相続財産になるのですが)が入るなんて詐欺だ」・「昨今の新聞でも書いてある詐欺だから警察に行こう」ということになり近所の交番へ行くことになりました。警察には資料を含め経緯を説明致しましたが、警察の民事不介入によりその場では解決出来ない形になりました。
結局、弁護士法に抵触する恐れ(弁護士法72条)があり、当職では解決できない案件となり、提携の弁護士に依頼することとなりました。
結局、その相続人の方は裁判所より呼出しがあり、県外より裁判所に出頭することとなりました。
その後、遺産分割申立事件になり審判という形でその相続人は相続分の放棄をし残りの9名での相続という結果になりました。
ポイント
今回の事例では、今の社会情勢(特殊詐欺等)の話が問題となっており特殊な事例かと思います。
通常のプラス財産が多い遺産分割事例であれば分与される側がいわゆる得(?言い方は良くないかもしれませんが)になる事例だと思いますが、昨今の社会情勢を考えるとそう思ってしまう方もいらっしゃるのかもしれません。
今回の事例に関わらず、調停・審判という形になりますと最低半年以上の年月がかかります。
(令和2年の司法統計によると、遺産分割事件の審理は6カ月から1年が最も多く、ついで1年から2年、中には3年を超える事案も多々あります)
さらに費用も当然にかかります。(遺産は減りますし、別のあらぬ争族を引き起こします。)
今回の事例の場合、通常は生活保護法の観点より、法律的には相続人は受給拒否は出来ないのではないかと思います。
ですが、個人情報保護法の関係上、区・市役所等からのなんの情報も公開がされず(本人が生活保護を受けているかどうか、また、情報公開されないのであればケースワーカーから相続人に説明してほしいと申し伝えましたが)連絡も取れない状況に陥ってしまいました。
通常であれば生活保護費は税金で賄われているため生活保護の一次支給停止等の措置が必要になるものではないかと思いましたが、区・市役所等からの遺産分割協議への協力は皆無でありました。
以上のように昨今ではこのような事例が出てきております。
大切な家族・親族等の為に遺言書の作成をされることが良い事例ではなかったでしょうか。
(追記として、昭和初期のご兄弟の中には生れてすぐに養子縁組でブラジルに行かれた方もいらっしゃいました。その方の消息は不明で、不在者財産管理人を専任した事例でもありました。)

ファミリータイズ山梨では、初回無料相談(概ね60分)を実施しております。
遺産相続・遺言・遺品整理・不動産(実家じまい)でおこまりでしたら、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
どこに何を頼んだらよいかわからない。そんな方、相続の専門家が親身にご対応させていただきます。
ファミリータイズ山梨では
初回無料相談(概ね60分)を
実施しております

遺産相続・遺言・遺品整理・不動産(実家じまい)でおこまりでしたら、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
どこに何を頼んだらよいかわからない。
そんな方、相続の専門家が親身にご対応させていただきます。
遺言書関連サポートの料金

ファミリータイズ山梨ではお客様一人一人に合わせたサポートプランをご用意いたしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【代表的な料金例】
●基本料金・・・・・3万円
●遺産分割協議書作成・・・・・5万円~
●公証役場立会(2名)・・・・・2万円
【代表的な料金例】
●基本料金
・3万円
●遺産分割協議書作成
・5万円~
●公証役場立会(2名)
・2万円
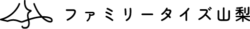
お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください

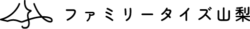
055-242-6166
まずは無料相談から9:00~1800(土日祝除く)
あなたとあなたの大切な家族のためにできること
あなたとあなたの
大切な家族のために
できること
一般社団法人ファミリータイズやまなし
行政書士ファミリータイズプラス
〒400-0043 山梨県甲府市国母8丁目14番50号
代表理事 廣瀬良太
宅地建物取引業 免許番号(山梨)第2663号
特定行政書士(第14160549)
宅地建物取引士(山梨)第4227号
古物商許可証 第471022024335号
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会(常務理事・常任幹事)
山梨県行政書士会会員
行政書士補 石川恵
一般社団法人ファミリータイズやまなし
行政書士ファミリータイズプラス